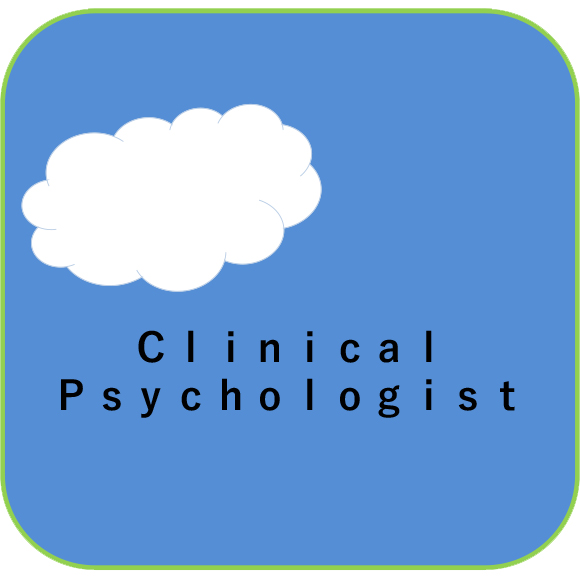子どもの夜尿・昼間尿失禁をあらためて 1
子どもの排泄
2025.01.18
メンタルヘルスや”発達障害”や不登校に関係する立場のひとに必須の知識として
なんでも「ブーム」がくればその後は常識になっていくことも(単なるブームに終わって立ち消えてくれていい話題もありますが・・・HSPみたいに)それが「あたりまえのこと」になるにはどうにもこうにも時間がかかるものですね。
いまは「なんでもかんでも”発達障害”」の感がありますが、ほんの10年ちょっと前までの30年近くは「そういうものではなくわがままなだけです」「親の問題です」などと一蹴されてきたものです。
場面緘黙はようやく認知は広がってきていますが、「どうしたらいいのか」にはつながっておらず、「おとなしい子」「声が小さい子」「苦手なことから逃げる子」とされたまま、ということはまだまだ見られます。
こどもの排泄に関連する問題についてはこれまでもお伝えしてきましたが、ここであらためていくつかの論文・解説をご紹介します。まずはスクールカウンセラーYさんが見つけてくれていたものから。
自治医科大学とちぎ医療センター小児泌尿器科の現在名誉教授でいらっしゃる中井秀郎先生
第27回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会教育講演(2019)
「あなたはCUTEを知っていますか?--今こそ小児の排尿機能異常に迫る–」より
(*太字 部分引用などさせていただきました。)
” (前略)排尿機能発達とその以上に基づく尿失禁(昼間尿失禁と夜尿症)が高い有病率で認められ、特に就学期や学童期の小児では、学校適応や心理状態に悪影響を及ぼす可能性があるため、適切な対応の策定が喫緊の課題となっています。”
” 一般的に切迫性尿失禁と夜尿症が代表的な症状です。これらの症状が子供に認められる場合、
上記 p10「はじめに」より
明確 な原因が見当たりませんが、おそらくは高次脳機能も含めた株尿路機能の発達過程との関連ガ疑われています。従来の対応は、楽観論(放っておいてもそのうち治る)、精神論(なんかの心理的ストレスがあるのかもしれない)、習慣論(躾の問題である)などに終始していましたが、近年、科学的根拠を重視した解明(EBM)が進み、本人や家族の精神的負担を軽減する意義や無治療キャリーオーバーの危惧が着目されるようになり、様々な科学的な診療が行われるようになりました。
以前もお伝えしていますが、夜尿症と便秘も関連が深いものです。ご自分のおこさんの便の状態や回数は、実際に目で見ることもないし、回数は尋ねても自己申告です。またこれも以前のコラムで取り上げていますが場面緘黙(社会不安)のあるお子さんとトイレの問題も見逃されがちです。排泄の問題が隠れた不登校の原因のこともありますし、気の毒なエピソードが生じればいじめにもつながります。
中村先生は現在都内のクリニックで小児泌尿器科の診療をされていらっしゃるようで、そこには夜尿症が改善した多くのこどもたちの声が掲載されています。お写真を拝見するとおやさしそうな先生…。羞恥や罪悪感をともないやすい症状にはこうした穏やかであたたかな表情や(たぶん)お声も大切な道具ですね。
「原則的な指導と記録をつけさせることだけでよくなるケースが多い」
「子どもたちもとてもうれしそうに見せてくれる」
とは お忙しい中ご相談に乗ってくださっているO先生からもうかがっています。
私も重症の便秘や夜尿症の改善で、みちがえるように明るくなった、意欲的になったお子さんの経験もしています。それまで服薬、アラーム療法などさまざまに行ってきた方でも、です。(ここて”すべて私が治せる!”みたいな話には受け取らないでほしいですが・・)ウロセラピーは「非薬物的、非手術的」ということで、それだけでも効果があるケースは多い。ということ。
それなのに!いっこうにこの問題の理解が広がらないのは大変残念です。
身長体重の健康記録と同じ水準で排泄の課題もチェックしていけるよう情報の提供を進めたいところです。
” 排便については、すでに排便習慣が自立しておむつの取れた幼小児では、腹痛でもない限り、子供の排便頻度や便性について保護者の注意は向かないのが現状です。保護者の多くは宿便や硬便の存在がしばしば昼間尿失禁の原因になることを知りません。”
CUTEとは:Child Urotherapy and Education とのことです。
この教育講演で「ウロセラピーの基本要素」として第一に「情報提供 demystification 種明かし 謎解き的な説明」と挙げておられます。これは強迫性障害でも 社会不安でも 摂食障害でも ”発達障害”でも面談をしているときに重要な要素と思います。診断は医療でするものであるといっても、その医療のサポートを受けたほうがいいという判断の根拠とその説明、そのときにこの「情報提供」の力が必要になります。平たく言えば知識とその説明の力といえます。
良質な「情報提供書」とは経過が書いてあるだけのものでなく、「本人が希望しているから」という説明だけではなく、自分がどう考えて何を伝えているのかも書いてあるもの ではないかと。
「医療への情報提供書はA4 一枚で」は真実か? はまた今度。
ところでなぜこの取り組みが広がらないのか。
それはひとえに保険診療のなかでは実施が難しいからでしょう。
” 欧米では昨今、この分野の専門ナースがウロセラピーを担当することが一般的になっています。我が国の現状では、ほとんどを小児科医か泌尿器科医の一部(小児の排泄症状に熱心に取り組む医師)が担っていますが、さながら「ひとりチーム医療」の惨状であり、短時間の外来診療で満足なウロセラピーができかねることは容易に想像可能でありましょう。”
上記P13
あらためて心理職にとってのこども排泄の問題:できること 知っておきたいこと をご確認ください。コラムを挙げておきます。次回は2020年の Health & Medicine での記事をご紹介。
臨床心理士として子ども排泄の困りごとに取り組む理由:便秘のこと①
臨床心理士として子どもの排泄の困りごとに取り組む理由:便秘のこと②